石橋大輔・札幌バプテスト教会牧師
札幌バプテスト教会の牧師の石橋と申します。バプテスト教会って「バスケット教会」とか「パブテスト教会」とかいつも間違われるので、紹介してくださった丹羽先生にもご苦労をおかけしました。教会付属の幼稚園であるひかり幼稚園の園長も兼任をしています。教会の一牧師ですので、学者の皆さんのように学識のある話ができなくて申し訳ないですが、現場からの声として一緒に考えさせていただければと思っています。
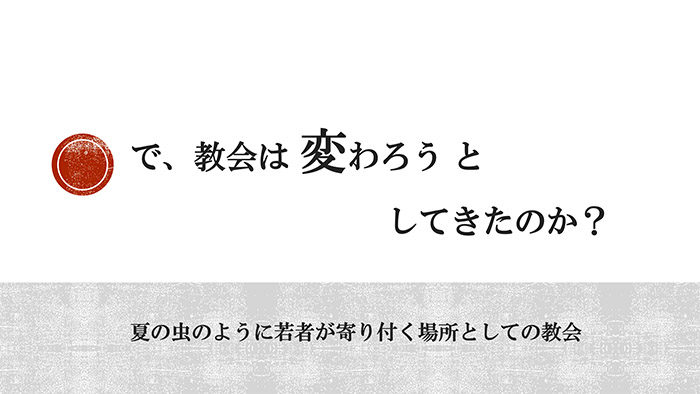
今日の発表のタイトルとして、「で、教会は変わろうとしてきたのか?夏の虫のように若者が寄り付く場所としての教会」というタイトルをつけさせていただいています。学者じゃない一牧師である僕に庭野平和財団の石井先生がお声掛けをしてくださったのは、2015年に北海道の北星学園大学で持たれた日本キリスト教教育学会での、「“若者”に“裏切られる”教会~キリストの信に生きる教会像~」という発題がきっかけでした。
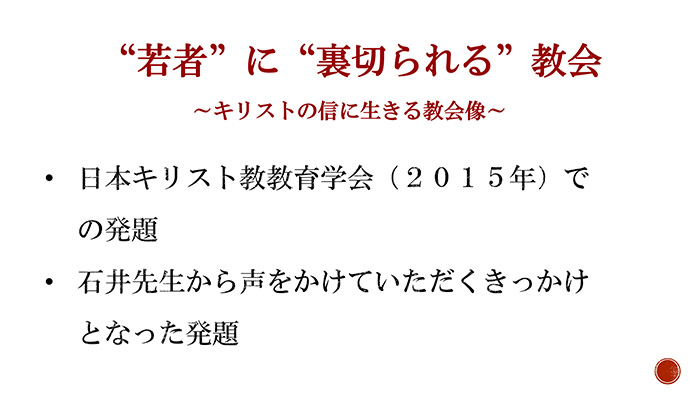
その発題の中で、一つの問いを立ててお話をさせていただきました。それは、「教会は誰を若者と呼んでいるか」という問いです。
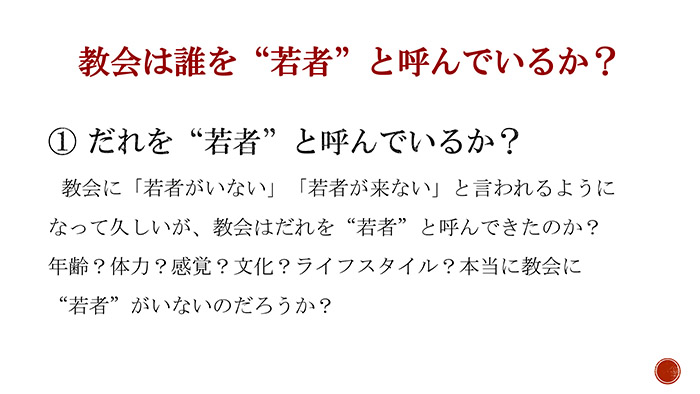
年齢的に若い人たちのことなのか。体力がある人たちのことなのか。感覚的な若さなのか。若者文化に生きる人たちのことなのか。ライフスタイルが若い人たちなのか。私たちの教会にも信徒会と呼ばれる信徒の集まりがありますが、年齢で区分されて分けられています。その中でいわゆる対象の会は、「少年少女会」と「青年会」と言います。少年少女会は13歳から18歳までと年齢で区分されていますが、青年会は年齢的な上限がはっきりとはしていません。以前は「結婚をしたら、その次の女性会や壮年会へ」というようなことがなんとなく暗黙の了解のように語られてきていましたが、もうそんな時代でもなくなってきています。なんとなくその他の青年たちとの話題が合わなくなってきたら、それとなく空気を読み、青年会から離れていく。ただし、壮年会や女性会とには所属したくないので、そのまま「無所属」になるというようなことがよくある状況でした。つまり教会は、青少年や若者について、それが誰なのかということをはっきりと定義づけしていなかったということです。そうであれば、そもそも教会が、「教会には若者がいない」と言うことすらできないんじゃないかと疑問に感じたのです。
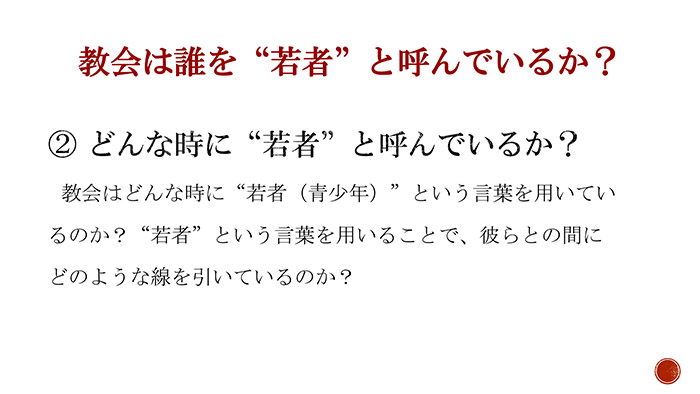
教会は、どんな時に“若者”という言葉を使っているんでしょうか?僕は教会がどこかこの“若者”という言葉を用いることで、そう呼ばれる人たちとの間に何らかの線を引いてしまおうとしているようにも感じました。その線を引くために、線を引きたいときに、“若者”という言葉が登場し、線を引きたい相手に対してその若者という言葉が用いられているのかもしれないというふうに考えました。教会では、僕自身もまだ“若者”という言葉を使って呼ばれることもありますし、他者に向かってそういうふうに呼んでしまうこともあります。自分自身が“若者”呼ばれて、いい気分もしなければ、いい意味で言われているわけではないと認識をしているのに、ついつい他者に向かって“若者”という言葉を使ってしまいます。
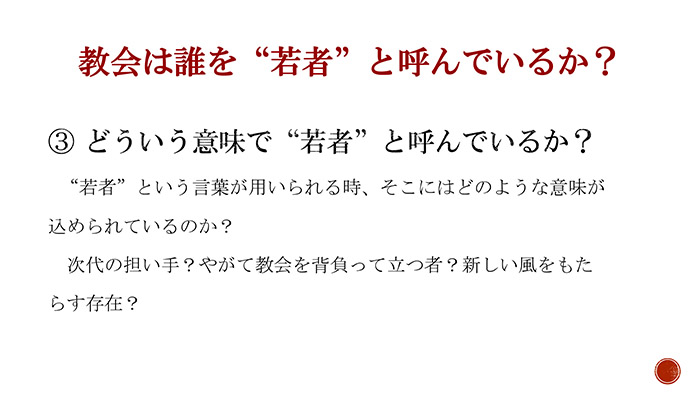
そこで、その“若者”という言葉の中身が何かということを考えてみました。次代の担い手ということでしょうか。教会を背負って立つものということでしょうか?新しい風を教会にもたらす存在ということでしょうか?そのどの言葉を取っても、決してネガティブな言葉として使われているわけではない。将来に向けて大きな期待が込められて語られている言葉だということはできると思うんですが、でもそれはあくまで「今」ではなく「将来」だということがポイントだと思うんです。その意味で、教会と若者とはどこか切り離された存在として想定されている。やがて教会を背負って立つ者ということは、今は教会で何を背負っているのか。次代の担い手ということは、今は何なんでしょうか?新しい風をもたらすということは、現在の教会には馴染んでいないということでしょうか?決して悪気があって使われてないにしても、この“若者”という呼称自体が、結果的には現在の居場所から“若者”と呼ばれる人たちを排除するということになっているのかもしれません。
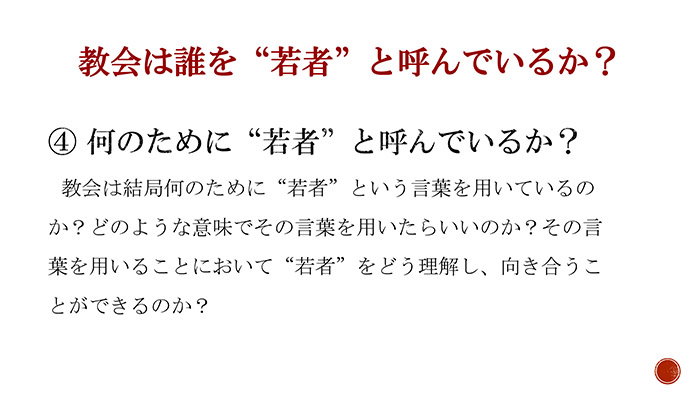
では、教会は何のために“若者”と呼ぼうとしているのでしょうか?教会ははっきりと定義付けもしていないのに、何のために“若者”という言葉、青少年というような言葉を用いているのでしょうか?そのことが問われなければならないんじゃないかというふうに考えました。 ここからは、現場でのいくつかの具体例をご紹介しながら問いを深めていきたいと思います。
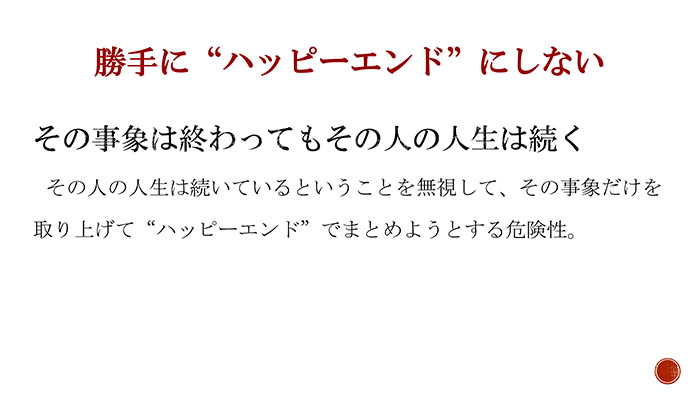
一つ目のテーマとして、「勝手に“ハッピーエンド”にしない」というテーマを掲げました。これは、僕が若者たちとの関わりの中で、何度も失敗を重ねて教えられてきたテーマです。 一時期教会を離れていた青年が、教会に戻ってきた時、そのことがうれしい余りに、“帰ってきた”という一点を切り取り、“成功事例”のように教会の人たちにも紹介しましたが、実際には彼はまた教会を離れていくことになりました。それも、ぼくが彼を叱責したためでした。そして、それにもかかわらず、彼はその後も、向こうから連絡をくれ続けたのです。 そのやり取りをとおして、勝手に“ハッピーエンド”を仕立て、“麗しい恵みの出来事”としてまとめようと、その人の人生の一部分だけを切り取ろうとしてしまっていた自分の愚かさを本当に悔いることになりました。まるで自分が『放蕩息子のたとえ』の父親にでもなったつもりでいました。迷い出たのに更生して帰ってきた息子を迎え入れたような、そんな気持ちになっていました。ですが、そもそも聖書に書かれている放蕩息子の父親(神さまのこと)は、息子の更生などということには一切触れず、ただただ息子の帰還を手放しで喜び、息子を信じ抜いたという話として紹介されているのです。自分の姿などとは全く似つかないものであったのに、思いあがった僕は、後から大いなる思い違いを悔いることになりました。
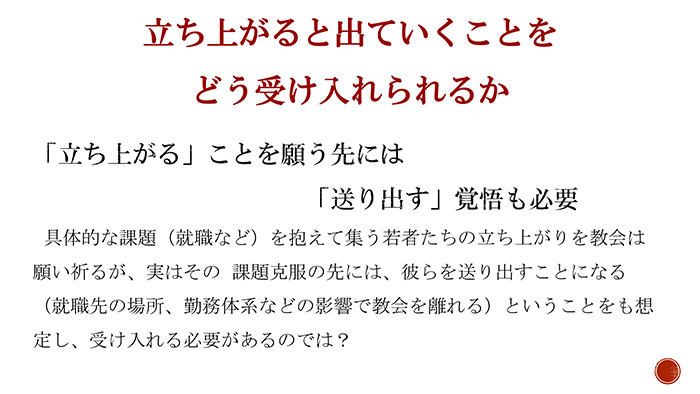
二つ目のテーマは、「立ち上がると出ていくことをどう受け入れられるか」というテーマです。教会が“若者”や“青年”という言葉を用いるときに、そこには理想の若者像が想定されているように感じます。リーダーシップの取れる青年。明るくみんなから好かれる若者。礼拝に毎週出席して奉仕を担ってくれる青年。きちんと献金ができる青年。青年の集まりでは新しいことにも挑むけれど教会の伝統を大事に重んじてくれる青年。そのような教会が一方的に抱く若者へのイメージです。そして教会はそのイメージに当てはまらなければ“若者”と呼ぼうとすらしないし、“若者”として数えようともしていないのかもしれません。 何人かの青年たちは、いわゆる“フリーター”とか“ニート”と呼ばれる状態で、教会に来るようになりました。毎日ハローワークの帰りに教会に寄っていく青年もいました。彼らが定職を求めてがんばっている姿を見て、ぼくら教会のみんなは応援し、祈りました。ところが、やがて彼らが職を得ると、教会以外に“やりがい”を感じる場所を見つけたことで、教会から足が遠のいていくことになりました。 教会のことが嫌になったということではなく、むしろ「ずっと応援してくれていた教会のみんなに、ようやく恩返しすることができた!」とでも言いたげな彼らの姿に、うれしいような、さびしいような、複雑な思いを抱いたことが忘れられません。 課題を抱えた青年たちが教会に通うことで再び立ち上がって歩み出していく。でもそのことを願う先には、やがて彼らを教会から送り出す覚悟も必要なのかもしれないということを考えさせられました。課題を抱えた若者を含めた色々な人たちが教会に来てくれます。しかし、特に若者はその課題を克服すると(それは一時的な克服でしかないのかもしれませんが)、やりがいを感じることのできるその現場を教会の他に見つけて教会を離れていくということが多々起こりました。そして一面では、教会もそれを願って祈っているのです。もちろん、「やがて教会から離れていきますように」と願ったり祈ったりはしませんが、具体的に職のない状態の青年が来れば、彼らが就職し、自立できることを願い祈るわけです。ただ、その先には、やがて彼らの足が教会から遠のく可能性も見据えておく必要があるのかもしれないと考えさせられた出来事でした。そして、「たとえ彼らが一時的に教会を離れることになったとしても、また何か大きな壁に衝突したときには、教会を必要として帰ってくるに違いない」と、そんなふうに彼らを信じる思いに裏付けられた姿勢が教会には必要なのかもしれません。
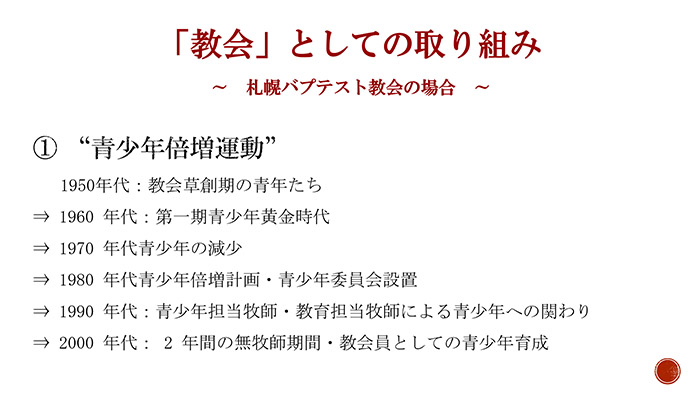
ここからは僕が働いている札幌バプテスト教会の青少年に対する具体的な取り組みの歴史を少しだけ振り返って紹介したいと思います。1953年に教会が創立されました。1950年代、60年代の草創期は、創立時に集まった若い人たちが中心になって過ごした時代でした。1970年代に入って、その人たちがだんだんと年を重ね、青少年は減少し、ある年、成人を迎える青年が一人もいなかったことを、教会は危機的な状況と捉え、80年代に入って“青少年倍増計画”を立て、“青少年委員会”を設置することになっていきます。青少年に対する働きに特化した“青少年担当牧師”も招聘され、教会の会堂とは別に、青少年が集うための建物も用意されました。いくつもの青少年対象の集会が持たれ、入り浸るようにして、青少年たちが多いときには100人ほど出入りをしていたということも聞いています。その他にも、教会立のフリースクールが開設されるなど、盛んに若い人たちへの取り組みがなされていきました。2000年代に入り、それまで複数いた牧師たちが期せずして同時期に辞任をしたということで、2年間、牧師がいない時期を挟んで、その後もう1人のベテラン牧師とともに、僕も青少年を担当する副牧師として呼ばれることになりましたが、その時も、教会の信徒によって青少年委員会は働きを継続していました。
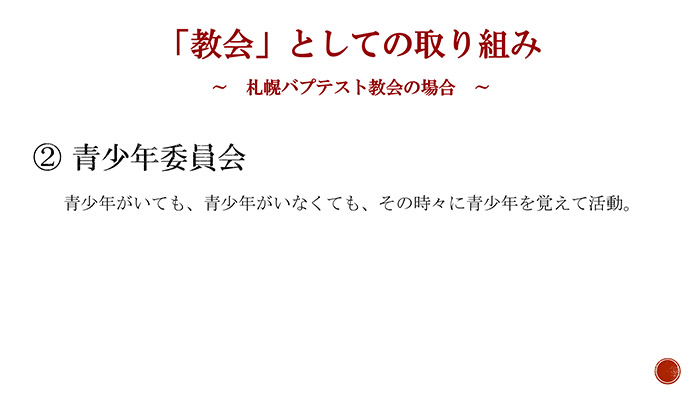
ただ、当時教会で“青少年”と呼ばれる層で活発に活動していたのは、ほんの一握りのメンバーでした。そこで、青少年委員の方々と話し合いながら、様々な青少年対象のプログラムをもう一度立ち上げていきました。
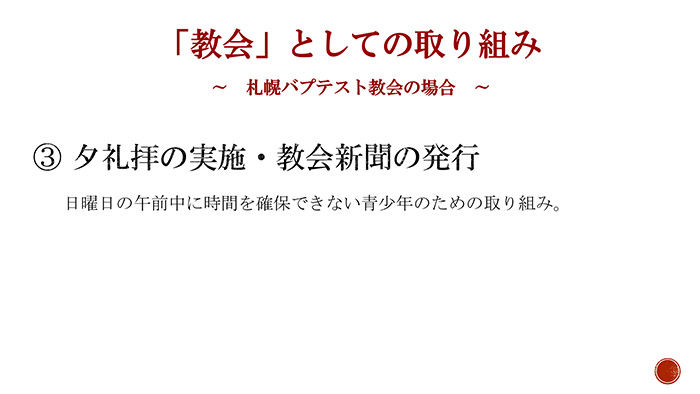
夕方に持たれている礼拝を青少年のための礼拝として実施をしたり、教会の新聞を青少年たちと発行したり、その他にも、青少年たちを連れていろんなところに遊びに出かけたりもしました。
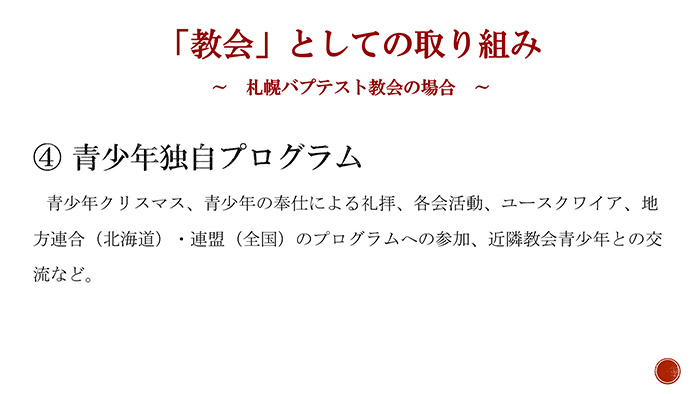
青少年独自のプログラムも打たれました。“青少年のクリスマス”や“青少年の奉仕による礼拝”、その他にも北海道や全国規模でもたれる青少年対象のプログラムに参加をするというようなこともなされていきました。
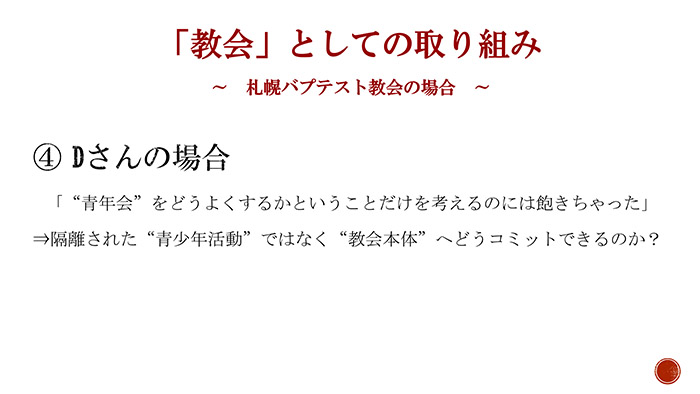
その中で、Dさんという青年が、ある時、「青年会をどう良くするかということだけを考えるのにはもう飽きました」と僕に言いに来たことがありました。それは、ぼくにとって、本当に衝撃的な発言でした。大人からすれば、「青少年たちだけが集まって何かの活動をした方がずっと楽しくやりがいのあることができるだろう」と考え、配慮のつもりで“自由”を与えていたわけですが、彼はそれを、自分たち青少年が、教会本体から切り離されていると捉えていたのです。そして「自分たちは、本来教会がやろうとしているその核になる部分からは遠ざけられ、何のコミットもさせてもらえないと感じていた」と訴えて来ました。
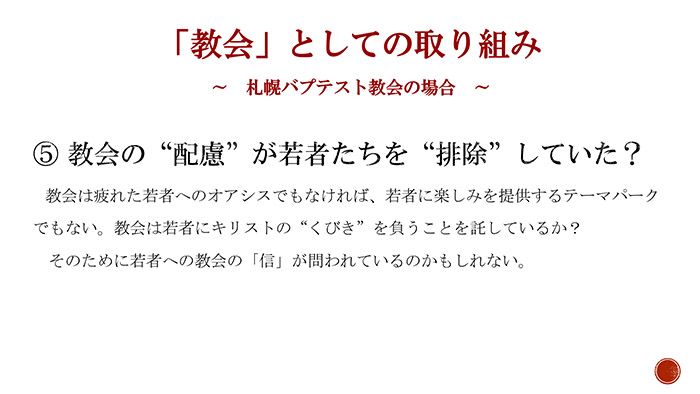
つまり、教会の配慮が、もしかしたら若者たちを教会から排除することにすらなっていたのかもしれないと考えさせられたのです。そう考えた時に、教会は、疲れた若者に対するオアシスや、若者に楽しみを提供するためのテーマパークになろうとしているのではないか。そうではなく、教会は若者も一緒に、神様から託された働きのために、キリストの“くびき”を共に負う必要があり、それをきちんと若者たちにも託そうとしているだろうか、と問われました。変に気遣うことで、教会が本質的に大切にしている一番の核から若者たちを遠ざけてしまっていたのかもしれない。一番面白いところは青年たちに託そうとせず、自分たちの手から離さず、握り続けていたのかもしれない。そんなことを問われたのでした。2015年のキリスト教学会では、このような発題をさせていただきました。
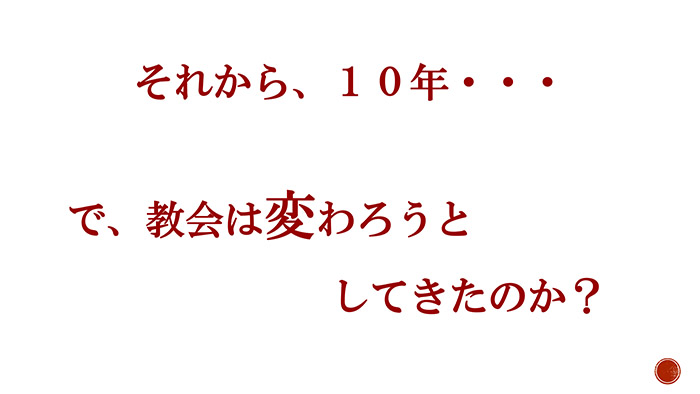
「それから、10年で教会は変わろうとしてきたのか」というのが今回の発題です。
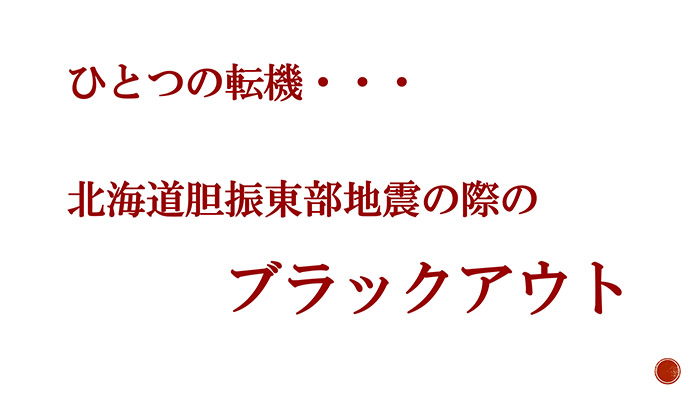
わずかながらでも教会が変わろうとしてこられたとして、その一つの転機となったのが、北海道胆振東部地震の際のブラックアウトでした。2018年9月に起きた震災によって、北海道全体が大停電に陥りました。

我が家に6人子供がいるんですが、その6人の我が子がまだ幼児と小学生だったため、我々の家族も含めた子連れ家族が何家族か教会に避難して過ごしました。当然教会も停電をしていましたが、それぞれ冷蔵庫にあったものを持ち寄りながら、急場をしのいで過ごしました。不思議なことに、それから半日後、まだ近所のどこも電気がついていない中で教会にだけ電気がつきました。そこで、「何か自分たちにできることはないか」と話し合い、まずは水を配ることにしました。停まったのは電気だけでしたが、マンションでは停電によって水も上げられず、エレベーターも動かないという大変な状況だったからです。案の定、たくさんの方々が水を受け取りに来てくださったんですが、同時に「建物の中で充電をさせてもらえませんか」と言う方々が出てくるようになりました。停電していたわけですから、その必要性が一番高いのは重々わかっていましたが、最初は「一般の人たちに建物の中に入っていただくのはどうか」と躊躇していました。

それでも、次々みえる方々に口々に求められ、とうとう「どうぞ」と中に招き入れたところ、またたく間に情報が拡散され、教会のホールにたくさんの人たちが集まってこられました。そして、地域の人たちが代わる代わる充電しながら、教会でくつろいでいくということが起きました。その時来られたほとんどの人が、その時に教会に初めて足を踏み入れたという人たちでした。この後、この写真の2倍、3倍の人たちがひっきりなしに入れ替わりながら来られ、滞在されるという状況が、日付が変わる頃まで続いたのです。そして、その頃になってようやく他の家や店舗にも順々に電気がついていきましたので、この状態は、この一晩だけのことで終わりました。
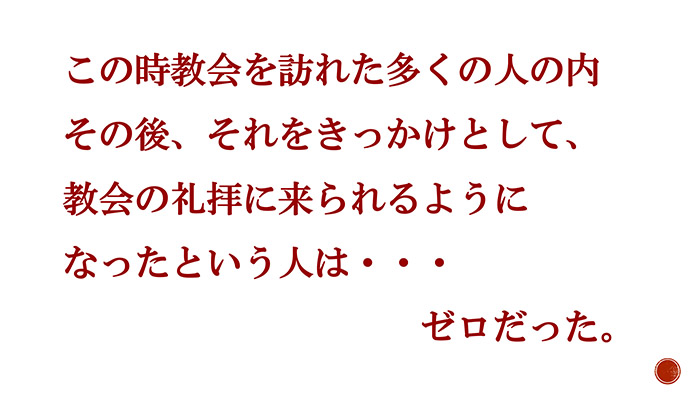
この時に教会を訪れた多くの人のうち、その後それをきっかけに教会の礼拝に来られるようになったという人は、ゼロでした。全くいませんでした。もしこのことを契機にたくさんの方がまた礼拝に来られるようになったということであれば、その時居合わせなかった教会の人たちも含めて、「教会全体の喜びの出来事」となったのかもしれませんでしたが、残念ながらそうはなりませんでした。
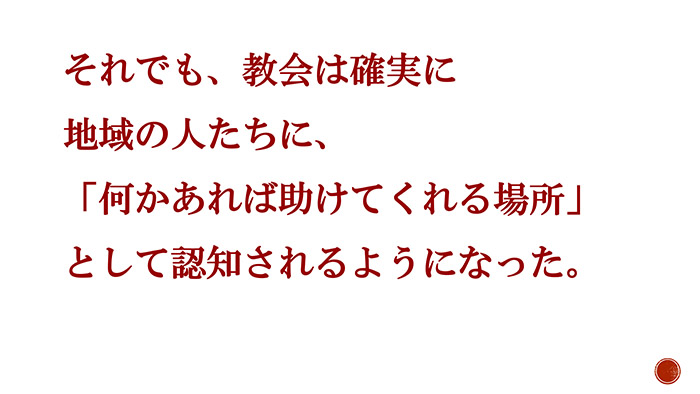
ただ、このことを通して、教会は確実に地域の人たちから「何かあれば助けてくれる場所」として認知していただくようになったと感じています。これまで、教会に来てもらうために、一生懸命にいろんなプログラムや集会を案内してきましたが、全く思いもしないような形で、たくさんの方が教会に出入りをしてくださったのでした。
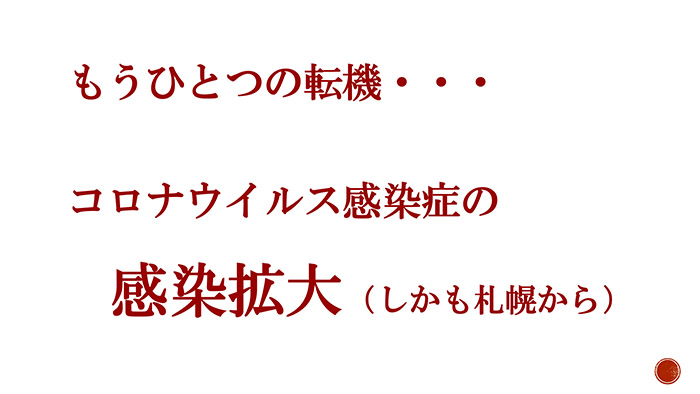
もう一つの転機は、コロナウイルス感染症の感染拡大でした。しかも札幌からそれは起こっていきました。ですから、様々な対策を講じるために、他の地域での取り組みを参考にすることができませんでした。何でも自分たちで考え、決断をしなければなりませんでした。ですから、その決断に対し、内外から様々な批判も受けました。
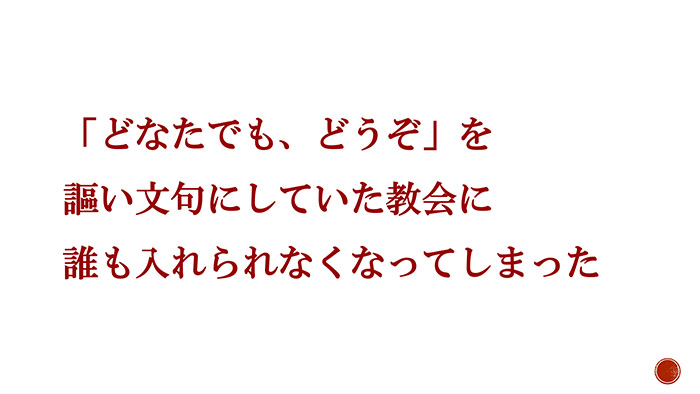
それでも、一番大変だったと感じるのは、「どなたでも、どうぞ」を謳い文句にしていたつもりの教会に誰も入ってもらうことができなくなってしまったということでした。「一体何をしていいのかわからなくなってしまった」というのがその時の本音でした。
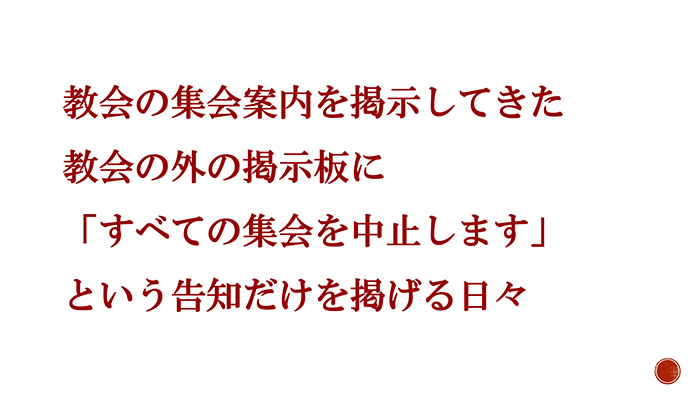
これまで教会で行っている集会の案内を掲示してきた教会の外の掲示板に、「教会のすべての集会を中止します」という告知だけを掲げる日々が続いていくことになりました。教会には誰も来ませんし、来させることができないので、そうしないための案内だけを掲示していました。
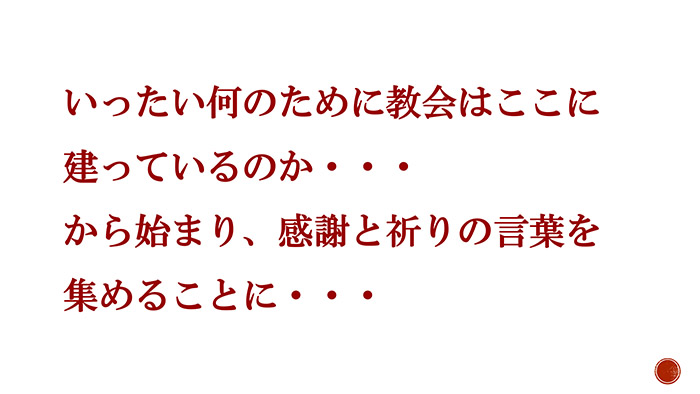
「一体何のために教会はここに建っているのか」と悶々と考えさせられる日々でした。そんな中、イースター礼拝の案内チラシが、配ることもできなくなって1000枚ほど捨てるしかない状態になっていました。それがもったいないということで、そのチラシのウサギのイラストの部分を切り取り、「何かに使えないだろうか」と教会の人たちと相談しました。結果、道行く人たちに、感謝と祈りの言葉を書いてもらったらどうかということになりました。外出もできず、口から出るのは愚痴と不満ばかりという状況下で、通りすがる人たちの心が少しでも明るくなればと願いました。
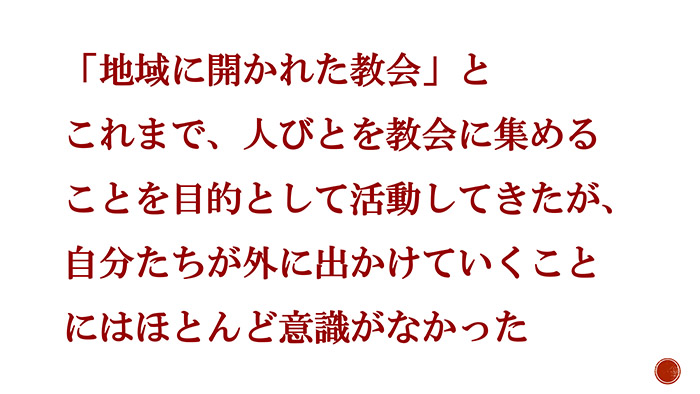
すると本当にたくさんの方々がそれに答えてくださり、掲示板に書いていただいた感謝と祈りのことばを貼ることができました。掲示板に入りきれなくなり、看板を出したり、ドアにも貼り付けたりというような形で、集められたその感謝と祈りの言葉が色んな形で拡がっていきました。これまでも「地域に開かれた教会を目指そう」と、教会でも標榜してきましたが、これまでは人々を教会に集めることを目的として、「扉を開けていますのでどうぞ入ってきてください」と案内をしてきました。でも、自分たち自身が教会の外に出かけていくことで教会が開かれていくということには全く意識がありませんでした。そのことを、このコロナを通して考えさせられたことでした。
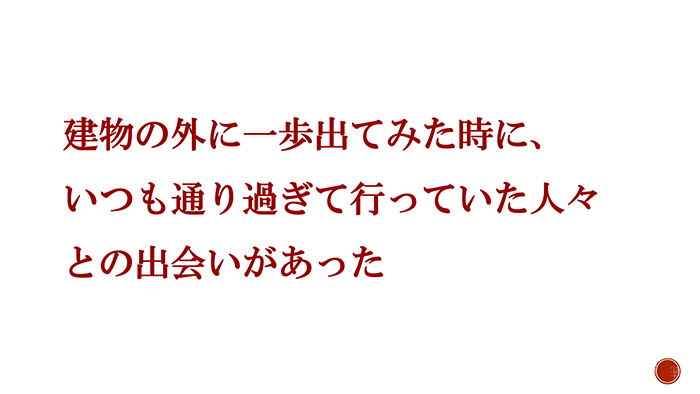
建物の外に一歩出てみただけで、これまで教会の前を通り過ぎて行っておられた人々との出会いがあることに気づかされていきました。
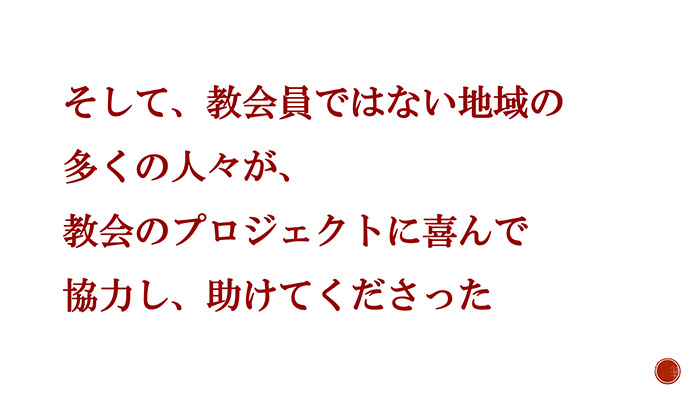
そして、教会員ではない地域の多くの人々が、教会のなそうとしているプロジェクトに喜んで協力し助けてくださるということも起こりました。そのことで、扉を開いて「中にどうぞ」とその方々を招き入れることで、実は教会の外の人たちに自分たちから出会おうとしてこなかった自分たちの姿勢を省みさせられたことでした。
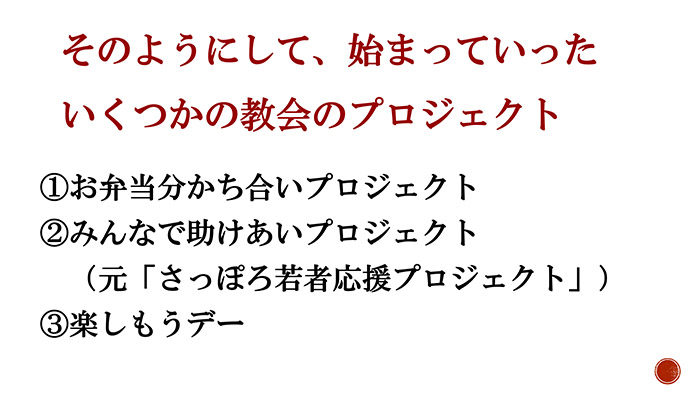
そのようなことを通らされながら、教会でいくつかのプロジェクトが始められていくことになりました。

一つは、毎週金曜日にお弁当を無料でお渡しをするというプロジェクトです。今では100人以上の方々に毎週お弁当を手渡しています。

それから二つ目は、もともと“さっぽろ若者応援プロジェクト”として始まり、今は“みんなで助け合いプロジェクト”と名前と形態を変えて行っている、年に二回無料で食料品や日用品をお渡しをするという活動です。多くの団体や個人から寄せられた寄付金や支援物資によって、活動を続けています。

それから、子どもたちに対しては、「楽しもうデー!」というお祭りをするようになりました。

この写真は、始まる直前の行列です。たくさんの子どもたちが来てくれます。コロナでどこにも出かけられない夏休みを過ごしていた子どもたちに、少しでも楽しいことを届けたいという思いで始めたお祭りです。

この写真は、お祭りの準備の時の写真ですが、地震の時にまだ小学生だった我が子を含めた子供たちが、中高生になって手伝ってくれています。この中高生が、なぜここで手伝っているのかというのは後でちょっと触れようと思います。
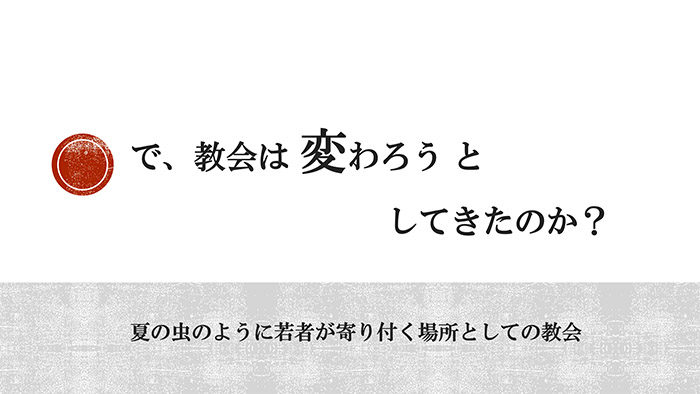
「で、教会は変わろうとしてきたのか?」ということで、
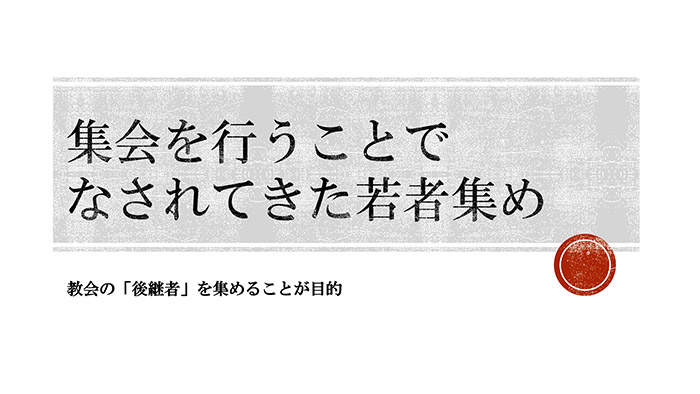
これまでの「集会を行うことでなされてきた若者集め」から、教会が若者にとって「居てもいい場所」、「帰ってくる場所」となっていること、いくことができるのかということが今問われているように感じています。うちの息子が中学生になった時、「信教の自由だ」と言って教会に来なくなりました。「確かに息子の言う通りだ」と、それを良しとして過ごしてたのですが、高校生になってからまた教会に来るようになったんです。なぜかと言うと、教会ではWi-Fiをつないでゲームをしたり、携帯で遊んだりして友達と過ごすのに、「こんなに便利なところはない」と気づいたからだったんです。そこから、複数の友達を連れて教会にくるようになりました。そんな理由でも、彼らがそこにいるということで、先ほどのお祭りの準備のように、何かをするときに一緒に手伝ってくれることもあるわけです。そして、そうでなくても、彼らのその存在そのものを教会が本当に喜ぶことができているか、若者がそこにいてくれるということを教会が喜ぶことができているか、と問われているように感じています。
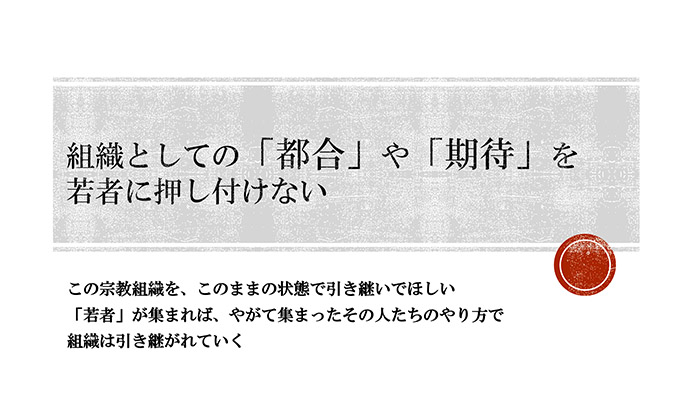
教会が組織としての「都合」や「期待」を若者に押し付けていないだろうか。押し付けないでいられていればいいなと願っています。「この宗教組織をこのままの状態で引き継いでほしい」という思いばかりが先立つと、そのためには「こんな若者が来ると困る」とか、「こんな若者に来てほしい」とか、そんなことを線引きしながら考えてしまいます。そして実際に来てくれている目の前の若者を、“若者”としてカウントしないというようなことが起こってしまうんだと思います。でも、“若者”と呼ばれる人たちが集い始めれば、やがて集まったその若者たちが、若者たちのやり方で、その組織を引き継いでいくことになるはずです。
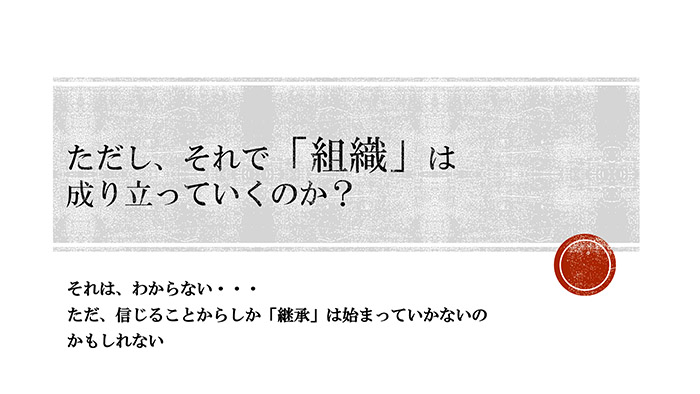
ただし、それで組織が本当に成り立っていくのかということについては、僕の中にもまだ疑問符が残ります。それでも、その若者たちのことを信じていく、そのことからしか、継承ということは、そもそも始まっていくはずがないと、教会という現場で過ごしながら感じさせられています。ご清聴ありがとうございます。